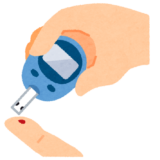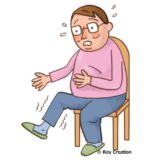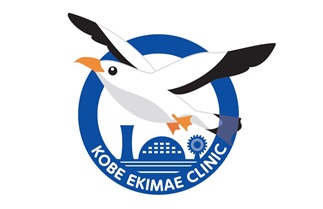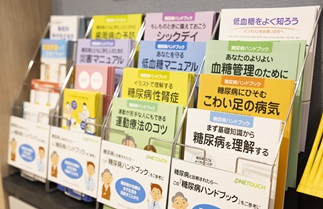糖尿病とは?
糖尿病は、血液中を流れるブドウ糖(血糖値)が増えてしまう病気です。
ブドウ糖は生命維持に欠かせない大切なエネルギー源ですが、必要以上に摂取すると、皮下脂肪や内臓脂肪として蓄積され、肥満や生活習慣病の原因となったり、血管を傷つける要因にもなります。
通常、糖分や炭水化物を摂取すると血糖値は上がりますが、膵臓から分泌されるインスリンというホルモンが働くことで血糖値が下がり、一定の範囲に保たれています。しかし、何らかの原因でインスリンの分泌が低下したり、体の中でインスリンの働きが弱くなると、血糖値が高い状態が続いてしまいます。
この状態を「糖尿病」と呼びます。
血糖調整のしくみ
血糖値が上がるしくみ
私たちは食物から栄養を摂取して生命を維持しています。ごはん、パン、麺類などは代表的な炭水化物を多く含む食品ですが、これらを摂取すると、その多くは消化の過程で腸の中でブドウ糖に変わります。
このブドウ糖が小腸から吸収されて血液中に入ると、血液中のブドウ糖の量(=血糖値)が上がります。
ブドウ糖は体にとって重要なエネルギー源であり、血液によって全身に運ばれます。
また、体にブドウ糖が足りなくなったときには、肝臓に蓄えられていたブドウ糖が血液中に放出され、血糖値が下がりすぎないようにする仕組みも備わっています。
血糖値が下がるしくみ
健康な人の場合、食事をして血糖値が上がると、その変化を膵臓にある膵β細胞が感知し、インスリンを血中に分泌します。インスリンは、血液中のブドウ糖を筋肉や肝臓、脂肪組織に取り込ませる作用があるため、結果として血糖値が下がり、食後の血糖値が上がりすぎないように調整してくれます。
一方、空腹時にはインスリンの分泌量が少なく保たれており、ブドウ糖が筋肉や脂肪に必要以上に取り込まれないようになっています。
このようにして体内の糖の量は一定の範囲に保たれていますが、糖尿病になるとこの調節ができなくなり、血糖値が高い状態が続くようになります。
糖尿病の原因には、インスリン分泌の減少が原因の1型糖尿病、食べ過ぎや運動不足など生活習慣の乱れ、またはインスリン抵抗性(インスリンが分泌されていても肝臓や筋肉でうまく作用しない状態)が原因となる2型糖尿病などがあります。特に太っている人は、このインスリン抵抗性が高いことが知られています。
糖尿病の症状
初期の糖尿病や軽度の高血糖では、自覚症状が出ないことが多く、糖尿病になっていることに気づいていない方も多くおられます。健康診断で初めて指摘される方も少なくありません。
しかし、かなりの高血糖になると、次のような症状がみられます。
のどが渇く、水をよく飲む(口渇・多飲)
尿の量が多くなる、尿の回数が増える(多尿・頻尿)
体重が減る
疲れやすくなる
これらは血糖値が高いことによる症状であり、治療によって血糖値が下がると改善します。
ただし、この段階で適切な治療を行わず血糖値がさらに上がると、重篤な糖尿病性昏睡に陥り、意識障害を起こすこともあります。
糖尿病の合併症
症状がないからといって血糖値の高い状態を放置すると、血液中の糖が糖化反応を起こし、時間をかけて体中の血管が少しずつ傷ついていきます。その結果、糖尿病の合併症を引き起こします。
代表的なものに、次のような「三大合併症」があります。
糖尿病性神経障害
糖尿病性網膜症
糖尿病性腎症
さらに、血管の動脈硬化が進むことで、足の壊疽(えそ)・脳梗塞・心筋梗塞などの「大血管障害」を起こすこともあります。
このほかにも、アルツハイマー型認知症・歯周病・がんなど、さまざまな疾患との関連が報告されています。